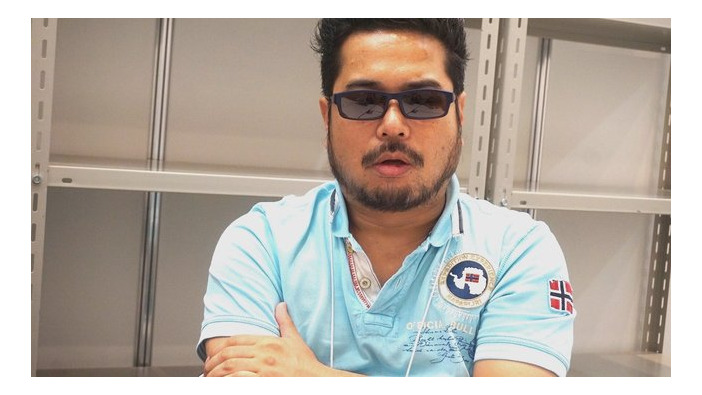バンダイナムコエンターテインメントが、PSVRの発売と同時にリリースした専用ソフト『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)』。PSVRを発売日に購入できた方の中には、同時に本作を楽しんだ人も少なくないでしょう。
本作の原型となる企画書がまとまったのは、約3年前となる2013年の11月。それから4ヵ月後の2014年3月に開発へ着手し、同年9月に『サマーレッスン』が発表されました。しかしこの時は、あくまで「技術デモ」という形であり、製品になるという話はまだありませんでした。

2015年に開催された「E3 2015」で披露された『サマーレッスン E3 2015 DEMO』
その後も体験会やE3などで、新たな世界が味わえる試遊体験を展開してきたものの、形態はあくまで技術デモのまま。そのため、体験会で魅力の一部に触れた方を中心に「ぜひ製品化して欲しい」という願いがユーザーの間で高まりました。こうしたユーザー側の盛り上がりも一因となり、2016年6月に念願の製品化が発表。PSVRと同じ発売日である10月13日にリリースを迎えました。

インサイドでは、この新たな一歩を踏み出すまでに、開発陣が当時どのような心境で制作に当たり、そして配信に向けて挑み続けたのか。その胸中に迫る開発者インタビューを本作の配信直前に実施。クリエイティプロデューサーの原田勝弘氏(@Harada_TEKKEN)と、プロデューサー・ディレクターの玉置絢氏に話を伺ってきました。
◆『サマーレッスン』の開発を振り返って

原田氏
──発表から2年が経ち、いよいよ発売を迎えましたが、まずは今の率直なお気持ちを教えてください。
原田:僕と彼(玉置氏)では感じているものも違うのかなと思っています。というのも、僕は本当に恵まれたキャリアのスタートだったんです。初代プレイステーションがローンチした時からキャリアが始まったので。当時、ナムコでポリゴンと言えば、表現は悪いけど「出せば売れる」みたいな勢いだったじゃないですか。『鉄拳』や『ソウルキャリバー』がワールドワイドで出れば、ミリオン行かなかったことがないくらいで。しかも、続編を出すのが当たり前といった雰囲気でした。
そういう中で育ってきたのですが、今回は違って、「やろう」となった最初の頃は、自分はすごくワクワクしているものの、社内で賛同してくれる人が少なく、形になるまでかなり苦労しました。本制作に至るまでこんなに長い道のりを歩いたのは初めてだったんです。
これまでが恵まれていたというのがあると思うんですけど、それだけに「こんだけ上手くいかないことがあるのか」と相当ギリギリ歯ぎしりしてました。それでもここまでこぎ着けることが出来たのは、ユーザーの後押しと社内でも協力体制が出来てきたからでしたね。なので、今までいっぱいゲームを作ってきてるんですけど、こんなに「モノが出ること自体が嬉しい」と思うのは初めてですね。それがまず、今までにない経験でした。
あともう一つ、若い世代と仕事が出来たのは、すごく嬉しかったですね。もちろんこれまでの仕事の中でも若手を育成してきましたが、僕は『鉄拳』にしても『ソウルキャリバー』にしても『ポッ拳』にせよ、スキルのあるベテランたちと仕事するケースが多いんです。ですが『サマーレッスン』は、プログラマーも『鉄拳』メンバーの中で一番か二番目くらいに若い人間が携わっていますし、玉置も開発当初は20代でしたから。僕は40代で、玉置は20代。この格差たるや(笑)。
玉置:誕生日が来てしまったので、今は30ですが(笑)。
原田:VRというのは新しいもので、それだけに今までの作り方では通用しない部分もあったんです。そのため、これだけ年齢差やキャリアに差があっても、「同じ悩みを共通で抱える」ということが出来たんですよ。若い世代とそれが出来たのは結構面白かったです。(これまでのようなゲーム作りならば)絶対ないことですよね、これは。だって僕の方が絶対に色んなことを経験してますし、何か作るにしても「こうだよ」ということが言えるわけです。でもVRでのモノ作りは「お互いゼロ」なので、新しく発見しないといけないことが8割くらいを占めてたんですよ。これは新鮮な体験でした。

玉置氏
玉置:最初のころは、原田さんが仰ったように、周りの理解を得るのが大変でした。でも時期が過ぎるにつれて、特にお客さんの反応がちょっと尋常じゃない感じを見て、「前に進むためにはやらなきゃいけないよね」という覚悟を持って下さった人が増えてきてくれたという実感がありました。「『サマーレッスン』どうするの?」と聞かれる時、昔は「やるの?やらないの?」という意味だったのが、やがてそうではなく、「どういう形でやるの?」という、やること前提の問いかけになっていたんです。そして「やった方が絶対良い、でも君はどういう形の答えを出すの?」という質問が社内で増え、みんなが「これはやらないとダメだ」と思うようになった転換期がありました。
で、僕目線から見ても、原田さんと仕事が出来たのは、やはり新鮮でした。普通はやはりトップダウンで、信頼されている人のアイディアやクリエイティブを、いかに現場で実現させるかが若手の仕事なんですよね。でも『サマーレッスン』では、“対等”ではないんですが、良い感じに張り合って進められたんです。「原田さんが仰るならそうしましょう!」ではなくて「原田さんが仰るのはわかりますけど、ここはこうやった方が良いと思うんですよ」という形でいられたのが、すごくやりやすかったですね。
もちろんVRが新しい分野だからとか、原田さんがそう配慮してくださったからとかもあると思うんですが、もう一つは自分にとって『サマーレッスン』のテーマ自体が得意というか、好きだからというのもありました。キャラクターと話したり、女の子キャラクターを題材にしたゲーム全般がもともと大好きだったので、その点に関しては「原田さんよりも僕の方が遊んでるだろう」と内心思っていたのかもしれません(笑)。
原田:ジャンル的に、彼はそちらの人でしたからね。僕はアクションとか人体制御とか、そういう方向だったので。だから、スタートの段階から結構ぶつかってました。「このゲームはアニメ表現でいきましょう」「ダメだダメだ!」みたいな(笑)。お互い、相手の発言にダメを出すようなところから始まっていったので、面白かったです。
玉置:そのやりとりも最終的には上手くまとまっていきましたし、もしその時に「いや、俺が3Dで良いと言ってるんだから3Dだ!」「はい、分かりました」みたいにやっていたら、良い形になってないだろうなと思います。
ちなみにその議論で結局、やるべきことは何だったのかと言えば、2Dも3Dもなかったんですよ。VRっていうのは、違う表現形式なので、アニメ調とかリアル調とか言っても仕方がないんです。そのことを実感したのはお客さんの反応を見てからですが、最初の一発目からVRならではの、ただの2Dでもまんま3Dでもない“丁度良い作風”が出来たのは、原田さんとのぶつかり合いや綱引きが出来る環境だったおかげですし、そのやり取りに加わって押し合いへし合いしてくれた開発スタッフのおかげです。これが、さきほどの原田さんのお話を受けての私の気持ちです。
あと、デモ版時代以降の話で言えば……「どういう形の製品にすれば良いのか」というのが、すごく大きな戦いでしたね。前例がないし、本作は明らかに普通のTVゲームの消費のされかたとは違うわけでして。お客さんの期待のしかたも違いますしね。食いつぶして楽しむような娯楽ではなくて、「体験」なんですよね。ある意味では、お金を払って旅行にいく、美味しいものを食べる、演劇を見に行く……そういったものに近いのかなと。

ですから、「こちらがどういうソフトを出すか」ではないんです。「お客さんがこのソフトにどう向き合うのか、どう向き合ってほしいのか」が大事で。そのための仮説を立てては上手くいくかどうか確認し、それを形にしていくのが一番大きな戦いでしたね。
ただ現時点の結論で言っても、まだ100%は分からないんですよね。「これがVR体験の完成形だ」なんておこがましいことは言えません。もちろん「ファーストコンタクトとして、これが正しい形だ」という自信はありますし、ほぼほぼ構想通りのスタートを切れたと思います。しかしその上で今後、お客さんにどういう感情を新たに受け取っていってほしいのか、これからどう展開していかなければいけないのか、考え続けている必要があります。
長期的にPSVRというハードウェアと、『サマーレッスン』というフランチャイズが、お客さんと良い関係を保つにはどうしたら良いかを、これからも考えていくことが、キャラクターVRの黎明期にある『サマーレッスン』にとって大事なことだと考えています。
──2年前にインタビューさせていただいた時に、「一緒に鍋を食べるレベルにまで持っていきたい」とおっしゃっていましたが、その辺りはいかがですか?
原田:今、ちょこっと見せてるよね。一緒にケーキ食べるっていう。
玉置:その点に関しては乞うご期待なんですけど、飲食という部分も含め、「人間」を表現するために生理現象を扱うというのは、すごく大事な部分なんですよね。なので、そこはかなり考えてやっています。そこらへんは、そもそも僕自身が反応を知りたいんですよね。人間のように見せる新たな仕掛けを作ってみた時に、自分自身もお客さんも、どういう風に感じるんだろうと。それが見てみたいので、いろいろと出していきますし、ぜひ体験して欲しいです。
原田:本当は『鉄拳』のブライアンと一緒に紅茶を飲む予定だったんですけども(笑)。
玉置:それがこんなことに(笑)。
原田:初代プレイステーションのポリゴン表現は超イノベーションでしたし、次はオンラインというイノベーションがありました。ゲームというものは、その時その時で大きな変化があり、作り手側が市場に衝撃を与えてきました。ただ、今までのモノと圧倒的に違うのは、VRは体験している人自体が極端に少ない点なんですよね。
一般的なゲームを遊んでいる人はもちろん多いので、例えば「悪い奴らを倒していく横スクロールのアクションゲームを作ろう」となって企画を見せたり、コンセプトPVを公開した時、ユーザーは「こんなゲームにして欲しい」「あのゲームを超えてくれ」とか言えるわけじゃないですか。基準がすでにあるので。でもVRや『サマーレッスン』の面白いところは、発表した時点ではまだ誰も遊んでないのに、期待だけすごく高まっちゃってたことですよね(笑)。さらに、体験会などでやった人はやった人で大騒ぎしてくれて。やった人とやってない人のギャップって普通は激しいんですけど、『サマーレッスン』でお互い「これは凄い」と同じような期待を持ってくれました。
例えば「『鉄拳7』出します」となったら、『6』がああだった、『タッグ』はこうだった、こんなキャラ入れてくださいと、ユーザーは言うわけです。でも『サマーレッスン』では言えないわけですよ。VRをやったことがないから。では「なぜ期待してるんですか?」と聞くと、「きっと良いに違いない」と返ってくる。こういうケースは非常に珍しいですよ。ユーザーが答えを持っていないんです。
だからこそ、面白い体験が出来るプラットフォームであると同時に、「どうすれば良いのか」と玉置が悩んでいた。答えを持つ人間が社内に誰もいないんです。

──制作側もまた、VRコンテンツの作り方の答えを持っていないわけですね。
原田:僕としても、「そこは玉置が考えてよ」みたいな(笑)。もちろん「こうじゃない?」とは言いますけど、それすらも正しいのかどうかは分からないわけで。そういう意味で言うと、正解を探すやり方は、本作の配信展開にも繋がってるのだと思います。「これで全てです!」ではなく、これまでも良い発見をしてきましたし、今も色々と発見しつつあるので、そういうものを発見できたタイミングで「これをどうぞ。こんなのもあるよ」と渡していけるようにしたいんですよね。
玉置:デモ版を作った時には、何をやっても新鮮な発見だらけという状態でしたし、製品版を作る時には製品版ならではの発見が数多くありました。製品版での発見で一番面白かったのが、「目の前でかわいい女の子が喋ってると気を取られてしまい、デバックがおろそかになる」ってことでした(笑)。セリフのチェックとかもイチイチするんですが、可愛い女の子に話しかけられるうちにボーッとしちゃって、内容が頭に入ってこないんですよ。そういう現象が起きてしまい、「あれ、今何を話してたんだっけ!?」って(笑)。
原田:積極的な人ほど、初めて遊ぶ前に「部屋の中を歩き回ってやります」とか「女の子を困らせてやります」みたいなことを言うんですが、いざ始めると緊張して動けないんです(笑)。「そこに人がいる」という認識をしてしまうと、存在を無視して机の上のオブジェクトをチェックしようと思っても、なかなか出来ないんですよね。それが今までのゲームと大きく違うところです。
例えば『鉄拳』の三島一八は、開発者である僕のことが見えてないから、一生懸命戦っているのに僕は地面を見て「ここのテクスチャ上手くいってないな」とか言えるわけで。でもVRだとダメなんですよね。頭ではわかっていても、本能的に相手をしちゃう。相手の話を聞いちゃうんですよ。

玉置:話も聞いちゃいますし、だんだん脳がやられていく感じになります(笑)。ボイスチェックのはずが、「うん……ああ……そうだよねぇ……」みたいになってしまって、気づくとセリフをチェックするところが過ぎてたり。消費するようなゲームではなく、体験として味わってもらえるようなソフトを目指して作っていったら、こういった新しい発見に出会えたというのは、ひとつの大きなポイントですね。
──『サマーレッスン』には、そういった新たな発見が積み重なっているわけですね。これまでのデモ版も体験させていただきましたが、製品版は「作り直してるのかな、これ」と感じるほど進化しているように感じました。
原田:色々新しくなってますね。PVではなかなか伝わらないんですが、VRを着けてみるとよく分かります。あと、僕は滅多に褒めないんですが、珍しく褒めてしまったことがありました。
──どんなことがあったんですか?
原田:一番最初に『サマーレッスン』の土台を決め、キャラを出して喋らせなさいと言って、そこから2週間後くらいに出来たモノを見たんですが、その時僕は激怒したんです。「あり得ない、なんだこれは!」「お前らは執念とか熱意はないのか」って(笑)。
玉置:普通の会社のオジサンみたいなことを言うんですよ!「俺が若いころは」とか(笑)。
原田:本当に「俺が若い頃は、こんな状態のものは見せなかった!」とか言いましたね(笑)。「そもそもこのキャラクターは腹が立つ。なんで腹が立つか考えろ!」とか。そうこうして、製品化する前に「ここまで出来ました」と言われて出されたものが、もの凄く良かったんです。顔の表情も素晴らしくて、素直にそう感じられるものになっている。最初の頃から考えると信じられないくらいでしたね。
玉置:あの時は一発OKでしたね。
原田:デモ版よりもよくなっていました。デモ版って、流れで5分やり切ればいいだけなので、集中して作れる分良いものが出来るんですけど、ゲーム全体をハイレベルで実現したのでビックリしましたね。
玉置:(見せた時)原田さんの反応が最初からポジティブだったので、「ああ、今日忙しいのかな」「早く話を切り上げたいから褒めてるのかな」と思ってたんです(笑)。でも次の日に話した時に「昨日の良かったよ」と改めて言ってもらえたので、ああ本当だったんだと。