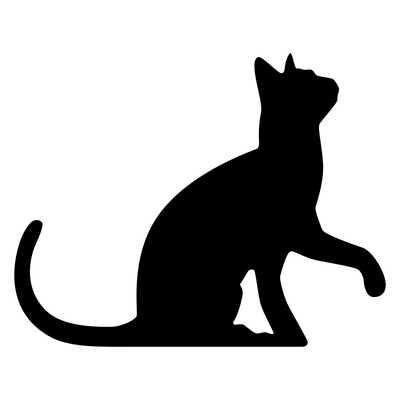本記事では物語中の重要な場面に言及しています。
必ずクリア後にお読みください。
2006年に登場した名作『The Elder Scrolls VI:Oblivion』以来、私達は「AAA級のゲームはオープンワールドでなければならない」という固定観念に囚われていたように思います。『Oblivion』によって現在のオープンワールドのスタンダードが確立し、膨大なコンテンツ、イベント分岐、キャラクタークリエイション……何かにつけて「自由度」という概念があらゆる作品で求められるようになりました。続編『TES V:Skyrim』の大ヒット、言わば「Skyrimショック」によってその流れは決定的になり、各社が競うようにしてボリュームの量を拡大してきました。今では100時間超えも珍しくありません。

コンテンツボリュームの増大は「遊び場」としてのゲーム空間を満たしてくれますが、大きなデメリットも抱えています。それは、「メインストーリーの密度が薄まってしまう」ことです。主軸となる波瀾万丈な物語に私たちは感情を揺さぶられますが、その途中で「寄り道」が多すぎると、肝心の本筋の出来事をついつい忘れてしまいます。いよいよボス戦が待ち構えるクライマックス直前、というところで、5時間ぐらい探索や事件屋ヒルディブランドのようなサブイベントを挟むと、せっかく盛り上がっていた緊張感も取り戻せなくなります。
オープンワールドに挑んだ『FF15』では、後半の緊張感のある展開をやるにあたって強制的な進行を採り、自由な前半の雰囲気との落差から賛否を巻き起こしました(個人的にはそれが最後の場面に効果的だったと思いますが、それは別の機会に)。それでも、仲間の不和やショッキングな死など、感情が大きく動く展開の時には一気に進めた方が強く印象に残るでしょう。オープンワールドはプレイヤー主導の探究冒険には向いているものの、物語への没入という点に於いては、主人公の感情を追うメインシナリオと相性が悪いのです。

『FINAL FANTASY XVI』のゲーム性は「Skyrimショック」以前の『FF12』と『FF13』を合わせたような設計になっています。モブハントやサブクエストでは、ある程度広いエリアを行き来する移動の自由はありますが、メインシナリオに沿って移動するときには、ほとんど迷うことが無い「一本道」に従って進みます。
撮影した動画を編集しているときに気がついたのですが、シナリオ進行中のプレイ時間のうち約7割は会話と関連バトルのイベントシーンで占められており、プレイヤーが自由に操作している時間が残り3割であることが多かったのです。

大きな要因は、イベントの合間にある目的地への移動が極限まで削られていることです。訪れるそれぞれの拠点では大抵聞き込みがあるのですが、真っ直ぐ次に向かったときの移動時間はほとんど1分以下、長くても2分以内で済みます。例えるならば「映画のオープンセット」として組まれた街くらいのコンパクトな規模に収まっています。

もう一つ、バトルステージ以外の野良モンスター戦闘はほぼ走り抜けて回避することが可能で、クライヴのレベルアップにはイベント戦闘だけやっても全く問題はありません。実際、チョコボに乗れるようになってからは全部無視して通り、「大河ドラマのアクション部分だけをプレイヤーが担当する」という感覚でした。システム的にも複雑な駆け引きやリソース管理も特になく、基本的には避けてカウンターを決めることに集中します。あくまでも格好良く見栄えするアクションで敵を倒す「殺陣」であるようです。


本作のマップ設計で感心したのは、エリア移動の要所で見える景色です。道なりに沿って進ませる利点は、遠景がどのように見えてくるか、絶景ポイントをどう見せるかが計算しやすいことです。
ファンタジー作品で見たいものと言えば、やはり神や魔法の力で創られた奇想天外な地形です。せっかくクリスタルを出すのですから、フォトモードで撮りたくなる景色が欲しくなりますね。広いエリアでフリーカメラだとプレイヤーがどの角度から景色を見るかがバラバラですが、本作では狭い道やエリアの切り替えポイントに「関」をつくり、必ず通る地点から見事な景色を見せる仕掛けです。ミニマップの廃止と相まって、そういうところでは自然とゆっくり歩きたくなるでしょう。オープンワールドでは失われてしまった「立ち止まる瞬間」がたくさんあり、旅情の体験として上質なものに仕上がっています。


フィールドとバトルの設計は物語の進行を邪魔せず、適度に合間を挟む、盛り上げるためにしっかり機能していると言えるでしょう。ストーリードリブンとしての極端さはシリーズや派生作品を含めても最も尖っているように思います。その最たるものはやはりバトルステージからボス戦に至るシークエンスで、突入から約1時間かけて息つく暇も無い展開を畳み掛けてきます。バトルとイベントシーン、さらにシリーズ名物のプリレンダムービー、これらがシームレスに流れていて、クライマックスに向けた緊張感の作り方はまさしく「ジェットコースター」でした。


映像表現の面は、一言で表すなら「換骨奪胎」です。さながらミュトスのように、他ジャンルエンタメの要素を「喰らって」創られているのは、プレイしていて特撮やアニメ、海外ドラマを連想させることからも明らかでしょう。シネマティックな演出に挑んできた『FF』シリーズとして、現時点でどんな表現ができるのか。良くも悪くもアニメ調の表現が主流になっている日本のRPGの中で、どうすればグローバルの最前線に立てるのか。その手段が「換骨奪胎」だったのだと思います。もちろんこれは悪い意味ではなく、ゲームの表現はここまで進化したのか、と驚きをもたらしてくれました。
生々しい血飛沫や残虐な殺し、大胆な濡れ場のシーンと、これまでのシリーズでは避けてきたものをここまでやるか、と言いたくなるほど盛り込む。20歳前後の青年だった主人公の年齢を30代まで一気に引き上げ(恐らくアナベラが事件を起こしたのと同じくらい)、モラトリアム期とは異なる成熟した大人のドラマにシフトしたのは、『FF』の今後を見据えた大きな改革ではないでしょうか。

音楽面では特定のメロディに物語の要素をリンクさせる「ライトモチーフ」という技法が印象的です。シリーズの他作品にもあるものですが、『FF16』では炎のモチーフなどの他に、初代から継承してきた植松伸夫氏の「プレリュード」と「メインテーマ」が様々な場面に登場します。『FF15』でも「プレリュード」が変奏としていくつかの曲に組み込まれていましたが、今作ではハープの音色がクリスタルと神にリンクして、分かりやすい形で流れていました。シリーズの代名詞とも言える2つのメロディが物語中のシーンに多く出てくるのは意外に少ないです(『FF14』も戦闘曲などでありましたが、シングル作品としては久し振りです)。

その上で、本作で新たに描こうとしていたのは何だったのでしょうか?ヒントは、初代から引用されたもう一つのライトモチーフです。それは『FF1』の「メインテーマ」(お馴染みの方ではないフィールド曲)で、人間の情念、作中で言う「自我」が露わになる場面で使われます。バハムートが暴走してクリスタル自治領が破壊される中、追い詰められたアナベラが「高貴な血」に執着する理由をぶちまけるシーン、その背景にマイナーアレンジした『FF1』の「メインテーマ」が流れました(サウンドトラックでは「Bloodlines」)。
アナベラにこの曲を当てるということは、『FF16』の主題はここにあると示しています。「できそこないの母」という彼女のコンプレックスが引き金でフェニックスゲートの悲劇が起き、その後の騒乱の元凶になってしまいましたが、最終的に「救世主の母」に収まったのは皮肉です。屈辱、野心、愛憎、哀れな末路で見せた絶望と狂気、それが人間の抱える業の深さだというのです。本作が宝塚歌劇団で舞台化されるとのことですが、アナベラがどのように演出されるのか観てみたいものですね。




登場回数こそ少ないものの、彼女の見せる様々な表情こそこれまでの『FF』に無かった表現ではないでしょうか。例えばクライヴ15歳のジョシュアを迎えに来る場面では、嫌悪の表情が顕著です。最初に訓練場の匂いに顔をしかめ、その次にクライヴに対して睨み付ける態度を取りました。このとき、嫌悪の特徴である「眉根に皺を寄せる」動きが描写されています。画面上はほんの僅かなものですが、プレイヤーはアナベラとクライヴの間に確執があることを一瞬で把握します。ここでは台詞は少ないものの、クライヴ、ジョシュア、アナベラ、ジル、マードック、この5人の関係性が視線と表情だけで分かります。『FF12』でも同様の演出はありましたが、今作では自然な演技として完成していました。
海外作品ではフェイシャルキャプチャーを用いた微表情の演技が増えていますが、日本の作品ではまだまだ少ない方。こういった演技の見せ方は、ゲームのストーリーテリングの成熟に欠かせないものになるでしょう。


クライマックスとなる召喚獣合戦の方では打って変わって、目も眩む程の光に溢れる迫力の巨大な激突が繰り広げられます。タイタン戦は次々に舞台を入れ替えながら、まさしく動く山を相手取りました。バハムート戦ではなんと成層圏をも突破して、ファンタジーはどこへ行ったのやら、某機動戦士もびっくりな極大ビームが発射されます。清々しいまでの外連味に振り切った超展開に、QTEの連打にも力が入るというもの。単体で観ればただただ圧巻の一言に尽きますが、目が肥えているとどうしても他の作品からの影響を感じずにはいられません。
それらの「既視感」を逆に無難な方法だと取る人も少なくないでしょう。『FF』だからこそ予想を超えたものを観たかった、そういう気持ちも分かります。また、血の匂いすら漂う生々しい表現と、人知を超えた外連味溢れる召喚獣合戦、明暗両極端で「時間帯の違う番組」の同居に戸惑いを覚えるかもしれません。それでも問答無用で気分が盛り上がるシチュエーションなのは間違いないですし、「このバトルが熱かった!」と思えればそれで成功ではないでしょうか。

『FF16』を遊ぶゲームとしてではなく、大枠の演劇作品としてみた場合、このバトルパートは映像ドラマの一部分であり、プレイヤーは主役の殺陣を演じる「役者」として劇に参加することになります。RPGの醍醐味は主人公になりきって感情を共有することですが、それに大きく寄与しているのが演出中にボタン入力を求める「QTE」です。本作の開発には『ベヨネッタ』で同様の演出をしているプラチナゲームズが参加しており、一連の召喚獣バトルが同社の「クライマックスアクション」の影響を多分に受けているのは確実です。
『ベヨネッタ3』のレビューでもQTEの仕掛けについて言及しましたが、使い方が悪ければストレスになってしまう諸刃の剣でも、きちんとお膳立てすればクライマックスをさらに盛り上げる極上のスパイスになります。批判を受けるような、予兆の短い突発的なものではなく、たっぷりと間合いを取って「ここだ!」というタイミングで押させれば、主人公が力を込める「決め」アクションと同期します。例えるならば、特撮ヒーローのショーで司会が「みんなで応援しよう!」と呼びかける場面ですね。子供達はヒーローの力になろうと一生懸命声を出します。上手いQTEにはこれと同じ効果があり、プレイヤーはクライヴと一緒に戦いの炎を熱く燃え上がらせます。

最後にアルテマをぶん殴ったとき、HPを削りきった技よりもきっと力が込められていたことでしょう。昔からイベントで攻撃ボタンを押させる仕掛けはありましたが、その究極がこのクライマックスに用意されたQTEなのです。
演出やストーリーが合わなかったという感想も多く聞かれます。それでも、上手く感情移入が乗りさえすれば、バトルと映像演出が一体になってこれほど熱い気持ちを滾らせてくれるRPGは『FF16』の他にない、私はそう断言します。

改めて考えてみると、RPGは観客=プレイヤーが「第4の壁」を超えて演劇の中に乗り込める舞台になっています。その上、主役をやらせてもらえるなんて他では絶対にできません。ゲーム性の粗なんて気にも留めず、「壁」の向こうの世界に自ら乗り込むのが何よりも楽しかった。物語の主人公としてストーリーから様々な感情を受け取り、自分自身の大切な思い出にしていった。ナンバリングのどの作品に触れたにせよ、ファンそれぞれが持つ『FF』の原体験とはそういうものではないでしょうか。
『FF16』ではシリーズを経るうちに「お馴染み」の枠に収まってしまったクリスタルや召喚獣、『FF1』から受け継いできた旋律を再構築し、現在のオーディエンスが新しい体験として触れられるようにしました。本作のプレイヤーは今後「メインテーマ」を恒例のEDテーマではなく、仲間達が集う熱い思い出の中に見いだすでしょう。使い古されて被った埃を磨き落とし、新たなクリスタルの物語として記憶に刻む。原点回帰、あるいは「古典復興」と言うべきこの試みは、日本RPGの潮流に投じられる大きな一石になるはずです。

最終的に『FF1』「メインテーマ」のフレーズは、変奏の形でラストのアルテマ戦(「All As One」)に鏤められています。言わば「自我のモチーフ」という新たな意味がこの旋律に与えられました。
人間の本質がどんなに汚らわしく醜いものでも、あえて抱えながら人として生きていく、これこそが全ての『ファイナルファンタジー』に通底するテーマである。そう高らかに宣言しているのだと私は解釈しました。
“こうして―クリスタルを巡る探求の旅は終わった”、『FF1』のオープニングと対になるこの言葉で本作は締めくくられます。“最後の幻想”かもしれない、そんな予感を残して。
同時に、《ファイナルファンタジー》と英雄ごっこに夢中になる子供達を映し、こう続きます。
“そして、新たな物語が紡がれていく――”
主人公になりたいと憧れる人々が絶えない限り、“究極の幻想”を巡る旅はこれからも続いていくだろう。かつて『FF』を遊んだ人たちが、新しい『FF』を生み出す担い手となっている今を表しているようであり、『FF16』を遊んだ人もいずれは、希望の灯火を携えてそこに加わっていく、そんな願いもあるのかもしれません。

これまでにシリーズが積み上げてきた遊びの幅を削り落としたが故に、物足りなさを感じて賛否両論になるのは必須です。しかし、10年後、20年後になって、『FF16』の熱気は最高だったよね、いやそうじゃないと、ある世代の共通体験として語り合える。それができる数少ないタイトルだからこそ、私たちは『ファイナルファンタジー』を求めてやまないのです。
良い点
物語と景色の見せ方、主人公とプレイヤーの一体感に注力した体験
一気呵成に畳み掛ける強敵との戦い
新たな息吹を与えられた『ファイナルファンタジー』のモチーフ
悪い点
「遊び場」としては物足りない
SDRでプレイした場合のサポートが不足している