
itch.ioに『JISEI』というゲームがあります。英語で紡がれる、とある「日本人」の辞世の句を、ただ追うように書いていくというもの。「散るをいとふ世にも人にもさきがけて 散るこそ花と吹く小夜嵐」。これは日本を代表する作家である三島由紀夫の辞世の句です。
三島由紀夫は今年で生誕100年。そこで本稿では彼に焦点を当て、Game*SparkのGW特集として、戦後華々しく登場し、苛烈に去って行った三島由紀夫がどんな人物であったかを紹介していきます。
さて、その前に……(itch.ioに『JISEI』あれど)「この記事、ゲームに関係ある……?」と疑う方もいるのではないでしょうか。まぁ、もう言い逃れできないのですっぱり白状しちゃうと、その通りで……ゲーム関係ありません!筆者も困惑している。
ことの発端は、筆者がGW用に書いた『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』に絡めた小説家・安部公房特集。これを書いたところ、編集者が「じゃあ文豪ウィークしようぜ!」と宣言し進められたわけで、博士課程での安部公房研究などでちょっとは近代文学を知っている筆者が書くことになった、という流れです。
三島由紀夫と安部公房は、真逆の小説家です。保守と革新レベルに小説のスタイルは違いますが……実は二人の仲は良好で交友は、三島の死まで続いていました。同じくノーベル賞候補となった作家同士というだけではなく、安部公房の生誕100年は2024年と、長い目で見ればほぼ同い年。ちなみに三島は大の蟹嫌い、安部は大の蟹好きという食い違いはあったそうな……。
というわけで、ある程度は知っているつもりだけど三島由紀夫を研究していたわけではない筆者が、ゲーマー向けに三島のエピソードなどをお伝えしていきます!なのでもし筆者が書いていない情報、オススメの作品などがあれば、コメント欄でぜひ追記してほしいと思います。謎の企画ではコメントの盛り上がりが命なのです。
「散るをいとふ世にも人にもさきがけて 散るこそ花と吹く小夜嵐」
三島は解釈が分かれる人物です。たとえば文学者として見ている層もいれば、過激な活動家として見ている層もいる。美の探究者として見ている層もいれば、コンプレックスが美しいと解釈する層もいます。それでもみなが惹かれ、長きに渡り読まれ、語り続けられるのが三島由紀夫という人間です。国内はもちろん、『JISEI』というゲームが海外で作られていることからも察しがつくように、国外でも愛されている作家なのです。
最初期の長編「仮面の告白」で文壇での地位を確立し、映画出演など、文芸だけにとどまらず意欲的に活動した三島ですが、自衛隊市ヶ谷駐屯地を占拠して切腹したヤバい人、という認識の方もいるのではないでしょうか。2020年には「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」も公開されましたし、政治的な側面にスポットライトが当たるのも仕方ないことかもしれません。

実際に彼を語るうえで、そうした“小説家の範疇を超えた活動”の数々は避けて通れません。有名なところで言えば「楯の会」といった政治活動や文壇にいた他の作家との交流、美輪明宏との交流やストイックな肉体美の追及。そしてなにより“天皇”に対する姿勢などが挙げられるでしょう。取捨選択をすればどこかに角が立つ、と思ってしまうほどに、彼の足跡はそのどれもが存在感に満ちています。筆者の好きな逸話は、安部公房との対談において自分に無意識はないと言いはなったところ。無意識を表現するタイプ(シュールレアリスム系統)の作家に向け、無意識すらコントロールしているとの冗談を言うあたりが実にかっこよく、人を惹きつけます。
しかし、当たり前ですがこれらは稀代の「芸術家」としての感性からくるもの。純文学において、その詩的表現を生み出す“精神”と、言動は往々にして関係します。この精神の一致からくる文体、小説群は(「花ざかりの森」もありますが)「仮面の告白」をもって文壇でも早々に認められました。傑物揃う昭和の文学においてもトップクラスと言って文句をつける人間はいないでしょう。たとえば(仲が良いとは言えない)井上ひさしも「自家製文章読本」の中で、三島の書いた「文章読本」を理論面で悪い例としつつ、それでも良い文章を書いているのが凄まじいと複雑な褒め方をしています。
その人気は国内に止まらず国外でもミシマとして有名です。感性的な世界が海外の読者に刺さったというのもありますし、フランスでフォーラムが開催されるなど依然として高い注目を集めています。
ノーベル文学賞とミシマ

ここで豆知識ですが、「純文学の国外展開」はかなり難しいのです。文章の芸術ですから、ひとつ間違えれば一気に読みづらくなるのが翻訳の大変さ。特に「日本固有の感覚」などを翻訳するのは至難なわけで、たとえば「夜、しだれ柳の下にたつ人影」と書くと、幽霊か闇討ちか……日本人ではそんな連想をするはずですが、外国人からは「夜、マホガニーの下に立つ人影」みたいな感じに見えているわけです(マホガニーは適当に選んだ木ですが)。だからまず「しだれ柳」だけでなく、日本文化そのものを知っている人間でなくてはいけません。(この辺はゲームのローカライズやカルチャライズにも共通する部分かもしれません。)
そして、ノーベル賞は英語に訳されないと選ばれないということも大きなハードルとなっています。実は日本で出版されただけでは選ばれないわけで、ハードルが高いのです。しかし戦後には日本人の文化をこれ以上なく理解し、同時に翻訳および国外に紹介をできる人物がいました。日本文学研究者のドナルド・キーンです。ざっくり、ノーベル賞に推薦できるほどの人、と捉えたらわかりやすいでしょう。
三島由紀夫は川端康成とかなり仲が良く、手紙のやりとりなどを頻繁にしており、その関係を師弟とみる意見もあるくらいに密接な関係でした。川端康成は、1968年に日本人初のノーベル文学賞を受賞しましたが、近年この時の候補に三島由紀夫がいたことも明らかになっています。
その時にドナルド・キーンは、三島の作品が優れていると思いながらも、まだ若く、これから先もっと素晴らしい作品を生み出すとして推しませんでした。これはドナルド・キーンの後悔として知られています。三島はその2年後に、自決しました。三島の自決がノーベル賞をとれなかったからなんてことは断じて言いませんが、一部の解釈では三島はノーベル賞を欲しがっていたとも言われていますし、事実ドナルド・キーンも深く悔いています。予想できない自決とはいえ、この苦しみはいかほどだったか想像すらできかねます。

で……なにがオススメなのよ!?
三島の小説は「仮面の告白」から始まり「金閣寺」「潮騒」「豊饒の海」と名作ぞろい。どれを三島由紀夫の“読むべき一冊”として挙げるかは人によって大いに分かれますので、あくまで独断と偏見での個人的好みを紹介させてもらうならば、(小説ではなく戯曲ですが)「籟王のテラス(ライ王のテラス)」という作品です。
これはタイトルに差別用語があるということで出版禁止になった作品で「決定版 三島由紀夫全集第25巻・戯曲5」という書籍でしか読めません。筆者は本当にたまたま図書館でこれを読み、(出版禁止の話を知らなかったため)なぜこの話が有名でないのだと驚いた記憶があります。
「ライ王のテラス」はらい病(ハンセン病)にかかった、アンコールの王ヤショーヴァルマン1世をモデルにした物語。彼の指示により建造された寺院が煌びやかに出来上がっていくかたわら、病気の進行によって体が朽ちていく王が描かれます。
三島が残した最後の戯曲ですが、前述の通り読める手段は限られているので、図書館などでぜひ読んでみてください。ちなみに、「ライ王のテラス」はカンボジアに場所として存在しています。

筆者が恩師の小説家に譲ってもらったヤショーヴァルマン1世の(石像の)ポストカードは柔和な笑みを浮かべています。この石像には苛烈に命を削った絢爛な王の面影はなく、やはり「籟王のテラス」で描かれた王は三島由紀夫の美意識なのだろうと思わせられます。
そして、小説や戯曲を読むのがひと苦労という人には、市川崑監督の映画「炎上」がオススメ。三島作品としても有名な「金閣寺」を映画化した作品ですが、その映像美は圧巻の一言です!
ここまでほとんどゲームと関係なく三島由紀夫について紹介してきましたが、生誕から100年経ったいまでも多くの人に読み継がれ、愛読者であることを公言する若い世代の著名人もいます。今回の記事執筆にあたって、もう少しゲームと絡められないか色々とデスクトップリサーチはしたものの、安部公房と小島監督のような関連性を見つけることはできませんでした。そして苛烈な生き方が影響してか、この先もエンタメの題材からは遠い存在なのかもしれません。(文豪をキャラクター化する作品はかなり多いのに、とにかく三島は出てこないですしね)
とはいえ、少しでも興味の湧いた方は、「仮面の告白」「金閣寺」「潮騒」「豊饒の海」、そして「籟王のテラス」といった文学作品を読んでみるのはもちろん、『JISEI』や「炎上」などで三島由紀夫の世界を覗くのも大いにアリでしょう。きっとGame*Spark読者と三島の間にも“ハードコアの皮を被った美を愛する者”というつながりが見出せるかも……というのは無理筋なオチですが!








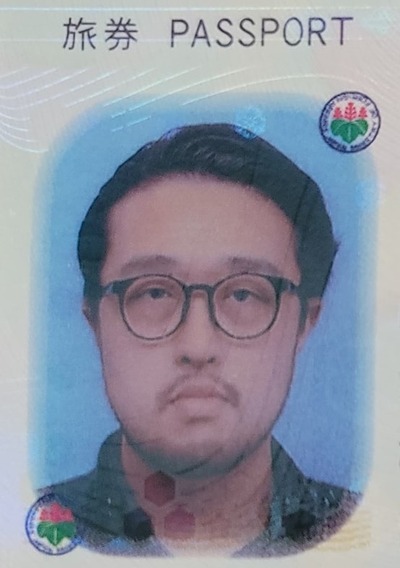


















※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください