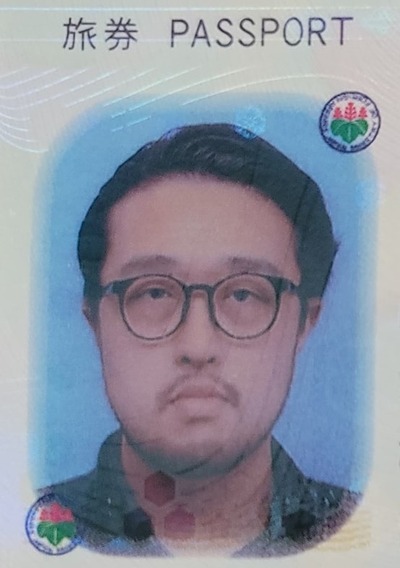トゥーキョーゲームスとメディア・ビジョンが開発し、アニプレックスがパブリッシングを担当するアドベンチャーゲーム『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』。
小高和剛氏と打越鋼太郎氏が共同制作するということで、『ダンガンロンパ』シリーズはもちろん『Ever17』や『超探偵事件簿 レインコード』、『極限脱出』、『AI: ソムニウム ファイル』など両氏の作品を数多くプレイしてきた身として、徹底的に遊びつくすしかないだろうと発売前から心待ちにしていました。

そして最終的にプレイヤーの手元に届けられたのは、なんと全部で100通りのエンディングに分岐するという特大ボリュームのアドベンチャーゲーム。しかもそれぞれのエンディングは差分のようなものではなく独自の内容になっているとの話も耳にしていました。
いくら何でもそんなことがあり得るのか?と半信半疑でしたが、プレイしてみるとその圧倒的ボリュームに驚かされました。発売から1か月以上たった今、レビューを公開するのも100エンドクリアに苦戦を強いられていたためです。

本稿ではそんな『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』について、Steam版100エンドクリア後の視点からレビューをお届け。なお、ゲームの構造に言及している箇所はありますが、物語については全ルートをプレイしての抽象的な感想・意見にとどめており、重大なネタバレは含まれていません。
謎が謎を呼ぶ職人技としか言いようがないストーリー展開
本作の舞台となるのは、消えない炎に包まれた学校「最終防衛学園」。「東京団地」からこの場所に連れてこられた少年少女たちが、学校を正体不明の敵「侵校生」から100日間守り抜く物語が描かれます。
少年少女たちに指示を出すのは謎のマスコット「SIREI」。『ダンガンロンパ』のプレイ経験がある方にとってはなじみ深いシチュエーションといえるでしょう。

「最終防衛学園」での1日はチャイムからスタートするところも『ダンガンロンパ』らしさ抜群。イベントのない日は仲間たちとの交流や素材集めなどを行い、イベントがある日は戦闘や特別な会話などをこなし、100日間を過ごしていきます。

前述のあらすじだけでも、消えない炎とは?何を防衛するの?侵校生の正体は?SIREIって何者?など、謎だらけであることが伝わると思いますが、物語を読み進めていくとその謎はさらに膨れ上がります。
また、何もない日々が続いて少しダレてきたか、というタイミングで新たな事件が起こりプレイヤーの心を掴み続けるストーリー展開はまさに職人技。小高氏の作家性が存分に発揮された物語を堪能することができます。

しかし、これは本作全体を見るとほんの一部にすぎません。ゲームのある地点に到達し、自由にルート選択を行えるようになってからが本番といえるでしょう。
物語のフレーバーの枠を大きく超えた手触りのいい戦闘パート
続いて、戦闘パートについてです。実は、プレイ前は物語のフレーバー的要素に過ぎないだろうと思っていたのですが、世界設定をゲーム性にうまく取り込みつつ、かなり考えて作られているという印象に変わりました。

本作の戦闘は、マス目に区切られたフィールド内で味方ユニットを動かし、敵ユニットを撃破していくターン制シミュレーションRPGシステムを採用。攻撃範囲はキャラクターや技によって、直線であったり十字であったりT字であったりと様々な形をしています。これらの技を使ってフィールド全体に無造作に並べられた敵を取り逃しなく倒す方法を考えるのはまるでパズルゲームのような楽しさがありました。

また、本作の戦闘をユニークなものにしている要素として「死がメリットになる」という点も挙げることができます。シミュレーションRPGでは基本的に「死=キャラクターのロスト」であり絶対に避けるべきもの。しかし本作では、死んでしまってもキャラクターをロストしないどころか、命と引き換えに放つ大技が存在するのです。

これらの大技は、命と引き換えで、あるいはゲージを消費して放つことができ、威力や攻撃範囲は通常の技より一段も二段も上。普段はパズルゲームのようにじっくり細やかに敵を倒していくことになるからこそ、一撃で大量の敵を倒す気持ちよさが引き立てられていると感じました。

ただ、戦闘パートと物語パートの接続に荒削りな部分が散見されるのが残念でした。例えば、戦闘では仲間とまとまって戦っていたのにムービーになると分断されていたり、目の前に敵がいて明らかに取り囲んでいたはずなのに直後の物語パートで隙をついて逃げたという展開になったりなどです。こうした違和感は他のゲームでもしばしば起こる問題ではあるのですが、本作は物語重視であるがゆえに違和感も大きくなってしまっていました。

なお、ここまでの戦闘に関する評価はすべて1周目や2周目までの話です。完全クリアを目指して周回し、キャラ育成が進むと1ターンで敵を殲滅することも簡単に狙えるように。しかし、そうなると戦闘が作業であるように感じられ、負担となってしまいます。
しかし、ある程度プレイを重ねるとゲームバランスが崩れることを見越してか、クリア済みステージ+類似したステージをスキップできる機能が搭載されているので、手作業ですべての戦闘を終わらせる必要はありません。

1.0.6アップデートによりスキップ可能な戦闘の基準がさらに緩和されたようなので、基本的にストレスなくエンディングを回収できるようになるはず。あとは戦闘スキップ時の演出時間の短縮に期待したいところです。

100エンディングの功罪
ここからは、本レビューの本題ともいえる100種類ものエンディングに関する話です。まず明確にしておきたいのは、本作のボリュームはノベル系のアドベンチャーゲームとして間違いなく規格外であるということ。
100エンディングすべてが真エンドになり得るというよりは、20個以上のルートが存在し、それぞれのルートの中に真エンド級のエンディングもあれば、あっさりと終わるバッドエンドもあるという構造です。しかしそれでも物量の暴力としか言いようがなく、差分抜きで600枚近くのスチルが収まるギャラリーは本作のボリュームを如実に物語っています。

これだけの作品を作り上げるのに必要な作業量は並大抵のものではないことでしょう。この課題にトゥーキョーゲームスは人手を増やすという方法で対処したとインタビューでも語られています。小高氏、打越氏を含めて総勢11名のライターがシナリオをルートごとに分担して手掛けたということです。
打越氏が手掛けたルート群では、点々と配置されていた伏線が一点に集中する打越氏の十八番ともいえる展開を存分に堪能できました。

合計で20以上存在するルートは、それぞれにおいて手掛けたシナリオライターの色が前面に押し出されています。個性をできるだけ出さないように統一することも可能であったとは思いますが、あえてルートごとに雰囲気をがらりと変えているように感じられました。
もちろん、どのルートであっても物語の基本設定(舞台や登場人物など)に違いはありません。しかし、内容や方向性が大きく異なるため、まったく別の作品を遊んでいるかのような気分にさせられます。

1本のアドベンチャーゲームの中で、同じ世界観のもとで作られた異なる物語を楽しむ...というのは中々ない体験ですが、「ある作品の二次創作アンソロジー・合同誌」を読んでいるような感覚というのが一番近いように感じました。にもかかわらずそれらすべてが本編であるという点が、本作を特別なものにしているのかもしれません。

このように、ノベル系アドベンチャーゲームに最も求められている要素であろう「物語」を、もはや複数の作品の詰め合わせといったレベルにまで詰め込むことに成功している本作ですが、その裏にはデメリットも存在しているように感じました。
その一つが、プレイヤーにとって合うライター、合わないライターが出てくる可能性が高いということです。ある1人のシナリオライターがゲーム全体を手掛けているのであれば、そのゲームが自分に合うか合わないかという話で終わりですが、本作の場合はそうはいきません。
11人のシナリオライターが手掛ける多種多様な100通りものエンディングが存在するため、プレイヤーの好みをピンポイントに撃ち抜くお気に入りルートを見つけられる一方で、それとは全く逆のルートも含まれている可能性も非常に高いといえます。ここは大好きだけどあそこはそうでもない...という複雑な感情がプレイヤーの中に生まれやすい作りだと感じられました。

また、もう一つ気になったのは、見事な伏線回収やどんでん返しを期待することが多いであろう小高氏・打越氏の作風と、この物量は相性が悪いのではないかという点です。
勘違いを防ぐために強調しておきますが、本作におけるメインのどんでん返し、プレイヤーをあっと驚かせる仕掛けは、これまでの作品に勝るとも劣らない素晴らしいものになっています。
では何が問題なのかというと、本作のボリュームに比例して本筋とは別に存在するサブ伏線とでも呼ぶべきものも膨大な量に膨れ上がっているということです。

もちろん、これらの仕掛けも職人技で作られたものなので品質は高く、メインとなる仕掛けの種明かしルートに到達してからも、他のルートでプレイヤーの興味を保つための要素として十二分に機能しています。
しかし、あまりにも量が多い。その1点につきます。あからさまに伏線だとわかるように描写されている要素はともかくとして、少し違和感を覚えつつもスルーしてしまうような描写についてはとても覚えきれません。
プレイ順によっては、3個目のエンディングで少し引っかかった描写についての種明かしが90個目のエンディングで行われるということもあり得るわけです。これが物語中、ルート中に無数にちりばめられていると考えると、一人のプレイヤーが一度のプレイで処理しきれる情報量をはるかに超えてしまっています。

そのため、Steamレビューなどでは、全エンディングを達成済みのユーザーであっても物語全体を理解しきれていないが故の誤った指摘を行っているケースも見られました。
これは私自身も例外ではなく、この描写は他のルートと食い違っているのでは?と思っている箇所はいくつかありますが、それを覆すような描写を見落としてしまっているだけかもしれないという疑念をぬぐい切れていません。
小高氏・打越氏の作品は何周も遊んで初めて気付くような細かな伏線や小ネタも多く、それを探すのも楽しみにしていたのですが、それを全ルート達成に当たり前に100時間以上かかる作品で行うとなると……。嬉しい悲鳴であることは確かなのですが、作風との相性は悪いように感じられてしまいます。

総評
アドベンチャーゲームを遊んでいて、クリア後にこの物語にもっと浸っていたいと感じたことがある方は多いのではないでしょうか?その感情に対して本作は驚くほどまっすぐに応えてくれます。
各ルートのシナリオは、首を傾げたくなるような内容のものもありはしましたが、大半は問題なくまとまっていたといえます。

100エンディングという周回プレイを主軸に据えた作品としては、テンポを悪くする要素が多いというのが問題点の一つでしたが、スキップ不可だったチャイム演出を飛ばせるようになるなど先日のアップデートにより一部改善されました。
今回のアップデートで改善された部分以外にも、100エンディング達成を目指す道中では、廊下にいるキャラクターの位置がマップ上でわかりづらいなどの点もストレスに感じていたので、今後のアップデートに期待したいです。

もしもあなたが100エンディングの達成を目指してプレイするのであれば、多様なシナリオが揃うが故に楽しくて苦しくもあるという、まさに狂気といえる忘れられない体験が待ち受けることでしょう。
筆者自身も心に突き刺さるルートに出会えた一方で、不必要であるように感じるルート、あるいは拒絶したくなるようなルートにも出会いました。正直なところ、今現在も本作に対してどのような感情を抱いているのか、整理がつきません。
アドベンチャーゲームとしてあまりにも長大であるため、一般的な作品と同じ割合だったとしても、楽しかった時間もそうでもなかった時間も長大になってしまう。膨大なシナリオの集合体であるがゆえに、端的に評価することが非常に難しい作品です。

個人的な筆者の体感としては、全体の2割ほどがペース配分やキャラクター描写などに難があり他ルートより明確にクオリティが低いと感じたルート、5割ほどが完成度が高く万人受けするであろうルートやファンの期待に正面から応えるような展開のルートでした。そして残りの3割ほどについては、色々な意味で攻めた展開であるなどの理由からプレイヤーによって好き嫌いが分かれそうだなと感じました。
攻めた展開とはどういった内容なのか……という点はネタバレになり得るので詳細は割愛します。本作はCEROレーティングで「セクシャル・暴力・犯罪」によりD指定となっている、ルートによって“攻め”の方向性は様々、この2点をヒントにどのような内容であるかはご想像にお任せします。

これから100エンディング達成に挑戦するという方がいれば、気になった部分のメモなどを残しながら遊ぶことをお勧めします。
また、特に最初のうちはどのルートから遊んだかによって、プレイ体験が大きく左右されます。今後の周回プレイへの意欲を強く掻き立てるルートや話を綺麗に終わらせてくれるルートに加えて、最初に遊ぶと訳が分からなくなったり本作に対する印象が悪くなったりする可能性があるルートが混在しているためです。
明らかに奇妙なルートに足を踏み入れてしまったかもしれないと察したら、フローチャートから別ルートに進んでみるのも選択肢の一つです。

好きなルートを満腹になるまで詰め込んで、また帰ってきたくなった時には異なる物語で出迎えてくれる。バイキング料理のような作品だったのではないかというのが100エンディングを達成し、振り返ってみての結論です。
Game*Spark レビュー『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』 PC(Steam)/ニンテンドースイッチ 2025年4月24日リリース
圧倒的な物量の中には、心から好きになれるものも拒絶したくなるものも混じりあう。歪な感情をプレイヤーに刻み込む怪作
-
GOOD
- 他に類を見ない圧倒的なコンテンツ量
- ファンの期待に応えるストーリー
- 1,2週目までは十分に楽しく、その後は(基本的に)スキップできる戦闘
BAD
- ゲームのテンポを悪くしている要素やクオリティが低いルートの存在
- 全てを理解したいのならばあまりにも膨大な時間が必要
《ライター:kamenoko,編集:宮崎 紘輔》
関連リンク
編集部おすすめの記事
特集
アドベンチャーゲーム
-
 フライパンで村を焼きまくりハーレムを築け!極悪女帝の人類殲滅乙女ゲー『ムラヤキヴィラン』【プレイレポート】
フライパンで村を焼きまくりハーレムを築け!極悪女帝の人類殲滅乙女ゲー『ムラヤキヴィラン』【プレイレポート】
最強攻め女魔王となって人類を滅ぼし世界を征服、さらにはハー…
-
 【TGA2025】コンビニの勤務が終わらないホラゲーや目的が“ベッドから出ること”なADVなど登場!「Latin American Games Showcases」「Women-Led Games」発表内容ひとまとめ
【TGA2025】コンビニの勤務が終わらないホラゲーや目的が“ベッドから出ること”なADVなど登場!「Latin American Games Showcases」「Women-Led Games」発表内容ひとまとめ
-
 ノスタルジック満載!2000年代東京が舞台のチルでエモな修理屋シムADV『リ・ストーリー 思い出修理屋』【プレイレポ】
ノスタルジック満載!2000年代東京が舞台のチルでエモな修理屋シムADV『リ・ストーリー 思い出修理屋』【プレイレポ】
-
 記憶が本になる異世界で“神の失踪”の真相を追え―ADV『Burden Street Station』初のデモ版が配信中
記憶が本になる異世界で“神の失踪”の真相を追え―ADV『Burden Street Station』初のデモ版が配信中
連載・特集 アクセスランキング
-

「まるでデビューアルバムを引っ提げた新進気鋭のパンクバンドそのものだ」海外レビューハイスコア『UNBEATABLE』
-

脳汁出まくり!放置系ポーカー『こんなのポーカーじゃない』で遊んだら一日が溶けた【プレイレポ】
-

とにかく突っ込め、戦略は後からついてくる!頭より体を先に動かせるSRPG『METAL SLUG TACTICS』パケ版発売記念プレイレポ
-
Logicool G「PRO X SUPERLIGHT 2C」と「G515 RAPID TKL」を試用!軽量マウス&ラピッドトリガーキーボードで“シューターのためのプレイ環境”を強化
-
『オクトラ0』マジでヤバい!8人バトルが最高に楽しい! 快適になったUI/UXと町の復興要素がシリーズ初心者も沼らせます
-
音楽が禁止された世界でバンド組み、反旗を翻す!リズムADV『UNBEATABLE』配信。公務執行妨害しまくりながらビートを刻め―採れたて!本日のSteam注目ゲーム6選【2025年12月10日】
-
超広大な廃墟島が舞台の終末サバイバルMMOFPS『PIONER』もうすぐ発売!協力レイドや釣り、カジノ、脱出モードなどコンテンツ多数【今週のインディー3選】
-
マルチもソロも楽しめるデッキ構築型ローグライク+すごろくボドゲが面白い/『イナイレ』チート対策で不正キャラが「不気味なニコちゃん」に/『NEEDY GIRL OVERDOSE』「とりい氏」「にゃるら氏」らにインタビュー【週刊スパラン11/28~】
-
2Dグラフィックがキュートな『リズム天国』ライクのリズムゲーが登場!日本語にも対応で“非常に好評”のスタート―採れたて!本日のSteam注目ゲーム9選【2025年12月11日】
-
フライパンで村を焼きまくりハーレムを築け!極悪女帝の人類殲滅乙女ゲー『ムラヤキヴィラン』【プレイレポート】