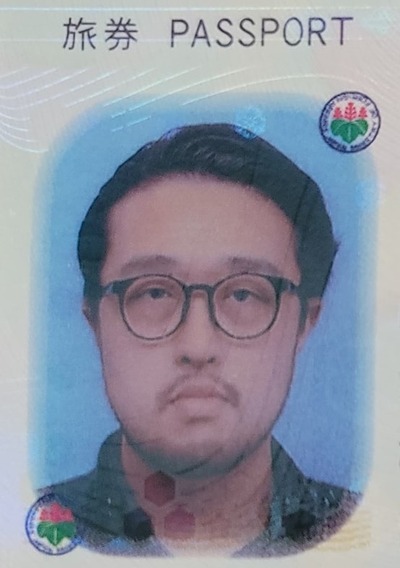2025年7月11日、中国・上海において、パルクールゾンビアクションシリーズの最新作『ダイイングライト:ザ・ビースト』(以下『ザ・ビースト』)のハンズオンプレビューが開催されました。
このイベントでは、各メディアが4時間というボリュームで、先行プレイ版の『ザ・ビースト』をプレイすることができたのです。そこで筆者が体験した『ザ・ビースト』の感想や、これまでのシリーズからの進化をたっぷりお届けします。
イベントにあわせて開発者のインタビューの機会も得ましたので、別記事にてまとめています。ぜひご覧ください。
※記事中にグロテスクな表現がありますので、苦手な方や未成年の方は閲覧をご遠慮ください。
ゲームプレイのために正当進化したディティール―意味ある「壁」へ目を凝らしてみよう

『ダイイングライト』シリーズといえば、無尽蔵のゾンビ達をいなしてマップを駆け回るパルクールアクションが目玉。パルクールには最適なロケーションが不可欠です。ゲームハードのスペックの向上と共に映像表現は向上するものですが、本作におけるロケーション表現のディティール(細部)の向上は、単なる見た目の良さではありません。パルクールアクションというゲームプレイの根幹を支える重要な進歩なのです。

これまでの『ダイイングライト』シリーズでは日除けやベランダなど、「出っ張り」や「角」「縁(ふち)」に当たるもの、図形でいえば「エッジ」のようなものを目で探して登攀するパルクールシーンが数多く登場しました。映像表現が強化された本作においては「エッジ」のみならず「面」のパルクールをディティールによって強化していると感じたのです。

骨組みの足場のようなどこでも掴める立体的な構造物ではなく、構造物の「面」である「壁」にも目を凝らす価値が生まれています。そこにゲームプレイの要素である、手をかけて登れそうな、わずかなミゾや穴があるのです。そして、実際にそれらを使ってグングン上へと登っていけるようにデザインされています。
そのため、今作では大きな壁面を見つけた時にそれをただの面と捉えず、注意深く観察する多様性が発生しています。ただの美しい街並みではなく、オープンワールドゲームの舞台として綿密にデザインされているといえます。


攻略の自由度を改めて体験。どのゲームも目指すべきゲームデザイン、ここにあり

これまでのシリーズで解禁が遅かった車が、序盤から使用可能でした。そして、この解禁に特定のクエストは必須ではなく、あくまで攻略の一手段だったのです。筆者は直近のクエスト拠点から離れ過ぎてしまうと考えたため、あまり車で移動せずに別のクエストで車での移動を提案されるまで使わなかったのですが、「クエストにとらわれず車をもっと使っていたらもっと快適にプレイできていたかも……」と思いました。
このように攻略の手段をマップ中で様々に発見することができるため、同じ目的を、プレイヤーごとに異なる発想で攻略できるという「オープンワールドの王道体験」ができるよう綿密にデザインされていると感じました。

徹底したゴア表現―悪趣味ではないがドギツさを感じるディティール

ゾンビを相手にするなれば、避けて通れないのがゴア表現です。筆者は、本作のゴア表現には激しさの中にあるビリーバビリティ(「実際にありそう」)を感じました。戦闘中に近接武器でゾンビの顔の皮が剥げたりや、探索の対象となる死体の表現の損壊された様子など、これまでのシリーズよりも幾分ゴア表現激しくなっているように思います。
また、画質やライティングの向上により、血や肉の質感が更に生々しくなっています。間違いなく、これまでホラー好きの筆者が経験したゴア表現の中で、最上級のグロテスクさでした。ホラーやスプラッタに慣れている人でも、本作を始めてしばらくは「キツイ……」と感じること請け合いです。

ゴア表現は様々で、王道の首切断、頭が上半分だけ欠損する、頭蓋表面だけがめくれて脳が露出する、口の皮だけが剥げる、更にそれらの複合……などパターンも豊富。こういった表現が戦闘中、プレイヤーのアクションに合わせてリアルタイムに発生することで臨場感が生まれていました。

ストーリーラインとスキルの連動―先の読めない展開と焦燥

ネタバレになるため多くは語れないのですが、プレイヤーであるカイル・クレインのしばらくの大きな目標は、レベルアップとは別軸の「スキル」の獲得となっていきます。注射によってカイルはどんどん能力(スキル)を獲得していくのですが、その度にカイルは苦しむのです。戦闘面でどんどん強くなるものの、その分人間離れしていっているような、不安。そしてそれがゲームクリアやカイル自身の目標にとって、どれくらい必要か分からないのですが、ゲームプレイのためについつい能力獲得してしまうのです……。二律背反たる思いに、プレイヤーとして心揺さぶられてしまいました。ゲームプレイとストーリーが上手く連動していると思います。

『2』と異なる軸のストーリー体験―世界がどうなるかではなく、あなたはどうするか

『ダイイングライト2 ステイヒューマン』(以下、『2』)では、対立した2つの陣営がストーリーの中心で、主人公がどちらに肩入れするかで展開が大きく変化します。一方で本作は「主人公がどのように復讐するのか、どこまで復讐するのか」といった問いかけを、強くプレイヤーに迫る内容であると、ハンズオンプレビュー中にも強く感じました。

『2』の陣営対立によって発生していたような「プレイヤーの介入により世界がどう変化するのか」ということよりも、「プレイヤーにどういう理由があって、どうしたいのか」というプレイヤーの心情(ゲームプレイにおける共感や、いわゆる「ナラティブ」)を重視されているのではないでしょうか。どちらのアプローチでも発生するクエストや入手できるアイテムといったゲームプレイの変化は起こるのですが、プレイヤーの心情的な理由に働きかける方が没入感は増します。
『2』はストーリーの変化の差の大きさも一つの魅力ですが、どちらの陣営にも肩入れしたくないような暗部があり、筆者はあくまで入手できるアイテムや設備というゲームプレイの視点でしかストーリー上の選択をしなかったのです。

一方で、『ザ・ビースト』では真逆の感覚を味わいました。例えば、拠点で暮らしている青年から、認知症になってしまい放浪している父を助けに行って欲しいというクエストがあります。人里離れた洞窟でその父に会ってみると、主人公を息子と勘違いします(あるある、ですね)。青年からは「父はアル中のろくでなしだった」と聞かされており、あまり同情心が湧かない背景があるのですが……息子のように振る舞うか、会話は無視して連れ帰ろうとするかはプレイヤーの自由です。彼が認知症の幻の中で何をしようとしているかはクエスト中明らかになっていくのですが……。

クエスト終盤、彼が主人公に御礼として形見を渡そうとしてきます。これを受け取ってもいいですし、それをクエスト依頼主の息子に渡すかどうかも選択できます。どれを選んでも、メインストーリーは変化しないことは間違いないでしょう。しかしそれでも、「クエストを依頼した息子が父をどう思っているか」、そして「父はなぜ認知症になる前、息子に嫌われる行動をしたのか」という情報をクエスト中で知った後では、プレイヤーにとって「アイテムなどのゲームプレイ以外で理由のある選択」をしたくなるように作られていると感じました。

4時間という限られた時間ではありましたが、ハンズオンプレビューでハッキリとシリーズの進化を示した『ザ・ビースト』。これまでのコンセプトを守りつつ、堅実かつ着実に総合的なゲームプレイを向上させていると筆者は感じました。
『ダイイングライト:ザ・ビースト』はPlayStation 5/Windows PC(Steam/Epic Gamesストア)/Xbox Series X|Sにて、2025年8月22日に発売予定です。