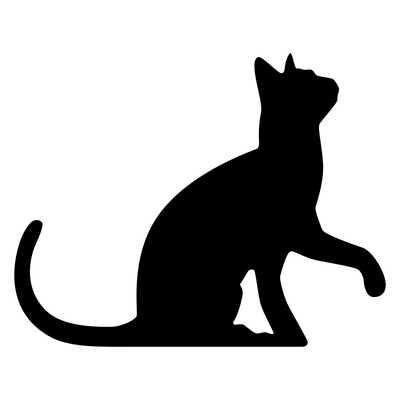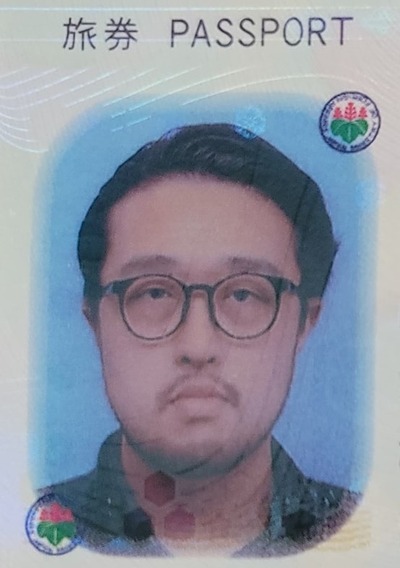今年度の賞レース大本命の呼び声高い『Clair Obscur: Expedition 33』(クレール・オブスキュール:エクスペディション33)。アーティスティックな映像と室内楽を基調とした音楽は芸術性を高く評価されています。素晴らしい作品ですから勿論タイトル名はしっかり覚えましたよね?大体の日本人はパティスリーとかブーランジェーリートかショコラティエとかしっかり言えるんですから、『クレール・オブスキュール』くらい簡単です。せめて「クレオブ」くらいは……。

インタビューでも言及されているとおり、タイトルの「クレール・オブスキュール」は美術用語で「明暗法」、イタリア語で「キアロスクーロ」と呼ばれる技法を指します。広義には明暗を使って立体的に描く様々な技法を包括していますが、狭義としてはカラヴァッジョに代表される強烈な光と影、光源が分かるくらいのハイコントラストの表現(テネブリズム)を指します。

カラヴァッジョの明暗法を代表する「聖マタイの召命」を例に観てみましょう。薄暗い室内に左側の窓から光が差し込んでいます。登場人物の顔は明るく照らし出されていますが、光の当らない場所はとことん暗く、周囲との比較によっては真っ暗でよく見えないほどです。まるで強いストロボで一瞬を切り取った写真のような画面です。

それまでの絵画は宗教画がメインであるのもあって、神の光が全体を照らすように淡く明るい色彩が多く使われていました。ルネサンス頃の画材の発展によって初めて暗色が濃く描けるようになり、レオナルド・ダ・ヴィンチやラファエロが陰影を使った表現を試みています。ゲーム的に言えばPS2の時代では難しかったシャドウや光源の表現がPS3、PS4でリッチになっていったのと似ています。
カラヴァッジョはパトロンを得られるほどの芸術家でありながら、弟子も取らずローマのアンダーグラウンドの社会にも接近しており、暴力沙汰で頻繁に逮捕されるほどの「不良」な素行が抜けませんでした。最終的には殺人を犯して脱獄犯になり、ローマから追放されたまま死を迎えます。芸術家の中でも破天荒な部類に入るカラヴァッジョの生涯ですが、人間のダークサイドに接していたからこそ表現できた、斬首や死体などの生々しいリアルな民衆の姿は当時の人々に強い印象を与えました。

しかし、画としての評価は賛否両論でした。中近世の絵画は基本的に教会や貴族の発注を受けて装飾用に描くものです。当然それに相応しい表現に沿って描かなければ不適切だと強い反発を受けます。神話や聖書は神々しいアンリアルな世界で描写されるべきなのに、猥雑で暴力的な世俗の暗がりで描いたカラヴァッジョは誹りを免れませんでした。雑に例えると、教会側は港区タワマンポエムのイメージで発注したのに、カラヴァッジョから上がってくるのが新宿歌舞伎町の路地裏スナップショット、といった具合でしょうか。実際、「聖母の死」は骸の描写がリアルすぎるという理由など、いくつかの作品の受け取りを拒否されています。

その一方で強烈な光源によるドラマチックな表現は唯一無二のものとしてフェルメール、エル・グレコなどのフォロワーを生み、劇画的な表現が特徴の「バロック絵画」の先駆者と現在は評価されています。
カラヴァッジョが始めたハイコントラストの技法は現在の映像作品には欠かせません。分かりやすいものだとクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」シングルのジャケットですね。電灯が普及した今でこそこうしたライティングは簡単にできますが、それまでは唯一太陽だけが充分な光源で、夜になれば暖炉の焚火と蝋燭の明かりだけが頼りです。限られた時間の中で、光と闇が生み出す一瞬のドラマを捉えたカラヴァッジョは芸術の変革者と言っても過言ではありません。

『クレール・オブスキュール』は人間の寿命を司る「ペイントレス」が「画家」を意味するなど、美術や色をベースにした表現が多く含まれています。有名な「あの人」にはもう会えましたか?そしてインタビューによると「明暗」には物語の核心に通じる意味が込められているとのことで、タイトル名が何を表すのか気になったら是非自分でプレイしてみましょう。今年随一のマスト作をお見逃し無く。
¥7,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)